
【前話のまとめ】
○前回のテーマ
「サンスクリット語とパーリ語ってなんだゾウ?」
・お経の主な言語
➀サンスクリット語経典
インド語。文法を厳しく規定された文語調のもの。グプタ朝以降(4世紀~)に仏典の正当語となったが、13世紀初頭のイスラム教侵攻により殆どが消失。現在は一部の大乗経典を残すのみ。
②パーリ語経典
インド語。文法に曖昧な部分を残す俗語。南側ルートでスリランカ等に伝わった阿含経典に用いられている言語。現存する経典言語の中ではお釈迦さまの話し言葉に最も近いものと考えられている。
③漢語経典 / ➃チベット語経典
大乗・小乗共に多くの経典が現存。独自の思想的発展を遂げる。
⇒中国ではどのように仏教が受け入れられた?←今回から中国仏教編じゃゾウ。
第二十話「中国仏教の特徴を知りたいゾウ!」
注目ワード 「中国仏教」「儒教・道教との交渉」「各義仏教」「廃仏政策」「三武一宗の法難」「教相判釈」

今回から中国仏教編だね。
一緒に頑張ろう。

新たな気持ちでがんばるゾウ!
ええっと。前回まではインドの仏教のお話だったから、それが中国に伝わったお話しをするんだよね?

そうそう。
いわゆる北伝仏教のお話しだね(インドの北側ルートから伝わった仏教 ※第十八話参照)。
日本仏教はこの中国経由の教えを基礎としているから大切なところなんだけど。。。
さて、どこから話そうかな。

何だか歯切れが悪いね?
単純にインドのお経が中国語に訳されたって話じゃないの?

う~ん、それがそう簡単でもなくてね。
インド仏教の歴史が様々な仏典や思想が生まれた『発生期』だとすると、中国仏教はそれらの複雑な『受容期・変容期』とでも言うべきか。。。
同じ北伝仏教でも国家事業として正式に仏教を受け入れたチベット仏教とは異なり、またアショーカ王(紀元前268~232頃)の使者のもと直接的に仏教を継承したスリランカのような南伝仏教の国々とも異なり(※第十八話参照)、受け入れには次のような特徴があったと言われるんだ。
<中国の仏教受容における3つのポイント>
①儒教・道教との交渉
②廃仏政策
③新古の経典の流入

どういうこと?
説明プリーズだゾウ!

うん。今回はまず中国仏教を知るために前提として大切な、これらの特殊な事情についてお話ししようかな。
➀儒教・道教との交渉

まず➀の「儒教・道教との交渉」について。
中国には諸子百家(中国で生まれた様々な思想家や学派の総称)と言われるように多くの思想、文化が古くから栄えていてね。
特に儒教や道教は国の礎ともなった宗教なんだ。
「儒教/儒家」
孔子(紀元前552~紀元前479)を始祖とする宗教および哲学。父子・夫婦・君臣に関する理想的な人間関係を示す「三綱(さんこう)」、仁・義・礼・知・信などの道徳を示す「五常」の思想の中心に置く。
「道教/道家」
老子を教祖とする宗教および哲学。現世利益や不老不死の追求、神仙思想、無為自然を中心とする道家思想、また呪符・陰陽五行・巫術などの中国古来の民族信仰も含めた総称。

儒教は聞いたことあるかも!
家族や目上の人との関係性を大切にする宗教なんだよね。

良く知ってるね。
これらは日本人の価値観・道徳観にも関与していると考えられていてね。
例えば年功序列の考え方なんかはその影響が大きいかもしれないね。
道教は何と言っても仙人思想が有名かな。
「作為がなく自然のままであること(無為自然)」を理想とする哲学も有名だね。

仙人といえば『封神演義』だゾウ!

私も少年ジャンプで見たよ(笑)
仙人や妖怪が仙界を二分して戦うとてもスケールの大きい作品。元々は明代に成立した中国の小説だね。
少し脱線したけど、中国の知識人の間でもこれらの宗教は哲学的議論の中心にいたみたいでね。
仏教が伝来した当初は、一部そうした知識を通じて仏教思想を理解したみたいなんだ。
例えば道教・道家の「無」の思想に通じるものあるとして『般若経』の「空」思想を理解したりね。

慣れ親しんだ中国の宗教を通して仏教を理解しようとしたってことだね?

うん、そうした仏教受容の姿勢を「格義仏教(かくぎぶっきょう)」と言うんだ。
もちろん全てのお経がそれで理解されたわけではないし、後には仏典は仏典そのものから思想を読み解くべきという姿勢が主流となるんだけどね。初期にそういった姿勢が見られたのは確かなんだ。
こうした理解は仏教の教義に合致するものとは言えないかもしれないけど、仏教思想の中国定着に一役買っている面もあるんだよ。

なるほど。。
他にも何か影響はあったの?

時には儒教の立場から次のような批判もあったみたいでね。
①仏教の出家主義は家や家族の関係性を重視する儒教の教えに反する
②皇帝に礼拝しない僧侶の姿勢は君主と臣下の忠義を重視する儒教の教えに反する
③常に袈裟を纏うなど世俗の服装に縛られない僧侶の姿勢は礼を重視する儒教に教えに反する

確かに家を出て修行するお坊さんと家を大切にする儒教の教えは相性があまり良くないかもねぇ(~_~;)

うーん、実際どうだったのかな。
儒教的な孝の実践を説く『父母恩重経(ぶもおんじゅうきょう)』というお経が生まれるなど、仏教側からの歩み寄りも見られたみたいだし。。。
とにかくそうして儒教や道教と融合や反発という交渉を繰り返し、共存しながら独特の展開をしていく。
それが中国仏教の一つの特徴なんだ。

そうやって中国仏教の個性が生まれてくるんだね。
それじゃあ、②の「廃仏政策(はいぶつせいさく)」というのは??
②廃仏政策

うん、これは①とも関係するんだけどね。
儒教・仏教・道教の三教は中国歴代王朝の皇帝によって優遇される順序がガラッと変わってね。その序列次第でしばしば仏教も厳しい弾圧や粛清にさらされたんだ。
道教や儒教を国教と定めた皇帝が国益に沿わないとして仏教を弾圧するとかね。
そういった事態を仏教側からは「廃仏」や「法難」と言うんだ。

それは大変だゾウ!!
どんなことをされたの?

「三武一宗(さんぶいっそう)の法難」という特に大きな4つの法難が記録されているんだけどね。
<三武一宗の法難>
北魏の太武帝(在位424-452)、北周の武帝(在位560-578)、唐の武宗(在位841-846)、後周の世宗(在位954-959)といった4人の皇帝による仏教弾圧。各皇帝の名から一字を取り「三武一宗の法難」という。

僧侶の殺害や強制還俗、寺院の没収、仏像や経典の焼却などが行われたんだ。
「軍役逃れ」「税制優遇」「戒律を破り堕落する」等、そういった国益に沿わない僧侶を粛清するといった側面もあったみたいだけどね。
中でも唐代の武宗の法難は「会昌の法難(会昌は法難時の年号)」と呼ばれた唐全土を巻き込む大法難だったんだ。
道教の信仰に熱心だった皇帝武宗の政策により、26万人余りの僧侶の還俗、政府公認の寺院4,600ヵ所余り、非公認の小寺院40,000ヵ所余りが廃止されたと記録されているよ。

そんなに!!
よく仏教が途絶えなかったね。。。

それがね。
これらの破壊はその度に仏教の復興運動を生み、大きな転換期となって仏教の在り方に大きく影響を与えたと言われるんだ。
都市寺院に帰属した学問仏教とは別に、日々の生活を営みながら実践を重んじる現実的な仏教が展開していくという形でね。
中国でお念仏や禅が隆盛した原因の一つと考えられているよ。
頑丈な石窟寺院が多いのも廃仏政策の対策みたいだね。
論争はあっても13世紀のイスラム教侵攻にいたるまで直接的な破壊は無かったインド仏教とは明確に異なる環境だよね。

弾圧されるたびにみんな頑張ったんだね。
それに合わせて仏教の捉え方も変化を求められたってことか。。
じゃあ③の「新古の経典の流入」というのは?
③新古の経典の流入

これは中国の仏教受容を語る上で最も取り上げられる点かな。
「中国仏教」の発展は勿論多くの外来の僧侶の教化によるものもあるけど、それにも増して仏教経典の翻訳そのものからもたらされていてね。
長い時間をかけて漢訳された膨大なお経に基づいて思索や修行が重ねられたみたいなんだ。
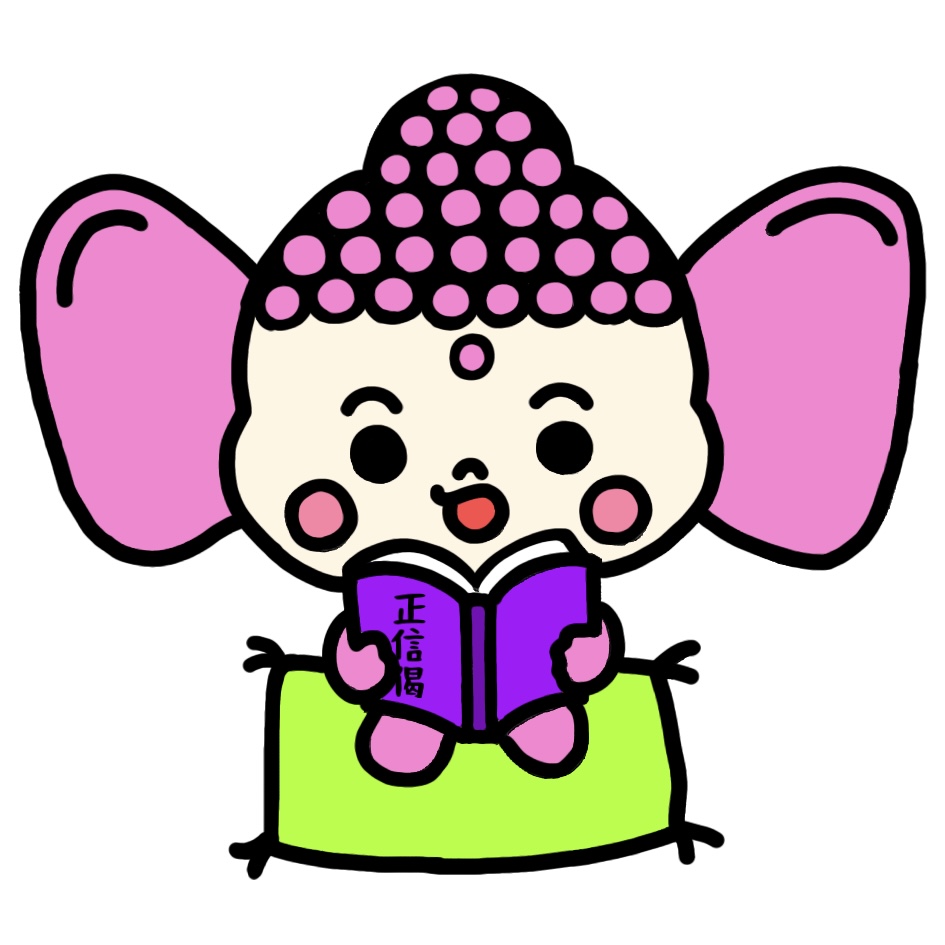
うん、日本にも沢山の漢訳のお経があるよね。

中国の偉大な訳経僧の成果だよね。
ただ、その膨大なお経も必ずしも組織的・系統的に中国に持ち寄られたわけではないんだ。
きくぞう君、インドのお経の成立年代の話を覚えている?

ええっと。
確か『阿含経典』という最初期のお経があって、そのあとに『大乗経典』が生まれたという話だったかな?


そうそう。
もちろんその分類が正解かは結論付けることは難しいのだけど、現代の仏教研究の成果の一つだよね。
その時代時代の仏教者が「お釈迦さまの伝えた教えの真意とは?」と問うて段階的に成立したものという考え方だね。
長い時間をかけてインドの人たちはそれを「仏説(仏が説いたもの)」と自然に受け入れていったんじゃないかということ。
ここで話を戻すけど、問題はそれらの仏典がそういった発展の事情に関わりなく中国に伝わったということなんだ。
例えば、最も原初的とされる『阿含経典』と後にそれを展開させた『大乗経典』が近い時期に届くとかね。

なるほど。
事情を知らない中国の人たちは当然全てのお経がお釈迦さま一人が直接説いたものと思うよね。
一見、違うことをお話ししているお経が一度に届く。
それって大変だよね!!
こんがらがりそうだゾウ。。。

そうだね。
距離の問題もあって一度に沢山のお経も運べないだろうし、当初は国を挙げての組織的な事業というわけでもなかったみたいだからね。訳して持ち帰るお経の種類も翻訳自体の巧拙も、その時その時の訳経僧の活躍に任せるしかなかったんだ。
そのような経緯でバラバラに届くお経をもとに仏教を学んでいくわけだから大変な混乱があったろうね。

中国の人はどう考えたの?

最も有名な対応は「教相判釈(きょうそうはんじゃく)」といってね。中国仏教を学ぶ際に必ず目にする言葉なんだ。
「教えの姿を判別して解釈を施す」といった意味合いかな。
本格的なものは、ある程度漢訳経典が出そろった南北朝時代(5世紀~)から確認できてね。
中国の学僧たちは次のように考えたんだ。
【疑問】
「膨大なお経はお釈迦さまただ一人がその生涯をかけて説いたものであるはず⇒なのにお経によって全く違うことが説いてあるように見えるものがある。なぜ?」
↓
【解釈(教相判釈)】
「お経の相違はお釈迦さまが教えを説かれた時期、また対象の素養や理解の段階に応じて説かれたため生じたのではないか!」

なるほど。。。
お釈迦さまがご説法された時期や聞き手の素質・成長でお経の違いがあると考えたんだね。

そんな感じだね。
そしてその分類法で最後に割り当てたお経こそが、お釈迦さまの教えの神髄・究極の教えだと定めたんだ。
この結論は学派によって見解が分かれていて、例えば天台大師から見れば究極のお経は『法華経』だし、賢首大師から見れば『華厳経』といった解釈だね。
これらの詳細はまた別の機会にお話しできたらと思うよ。

「儒教・道教との交渉」に「廃仏政策」に「新古の経典の流入」。
中国に仏教が伝わるには沢山の課題があって、それに対応するように中国の仏教も独自の発展をしていったんだね。

そういうことだね。
今回は中国における仏教受容の特殊な事情について代表的なものをお話ししたよ。
次回からはこの点も踏まえ、中国仏教を語る上において欠かせない訳経僧の活躍について一緒に考えてみようね。

よ~し、がんばるゾウ!
←第十九話「サンスクリット語とパーリ語ってなんだゾウ?」に戻る
→第二十一話「前漢~後漢時代の仏教を知りたいゾウ!」に進む
<よければこちらも!補足コーナー>
発想の全く異なる言語からの翻訳に伴う混乱。現代でも一つの単語の解釈だけで本一冊が出来るほど。当然翻訳僧の素養により巧拙がでる。
また高い中華意識の民族性のためか、元のサンスクリット語などの原文聖典が省みられることはなかった。
そうした事情に支配された側面が中国仏教にはある。
